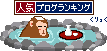『文明の災禍』=内山節・著
◇片方が脱落した社会の敗北
三月十一日以降様々な震災論、原発論が刊行されてきたが、本書はその中でも異色である。どこが異色か。復興の第一歩を「供養」としていることである。
ここで言う供養とは、形としての葬儀や祈りのことではない、これから生きて行かねばならない人間にとっての、死との向き合い方のことである。著者は言う。「(日本の伝統的な社会観では)社会とは自然と人間の社会であり、生者と死者の社会であった。社会の構成メンバーのなかに、自然と死者がふくまれていた」と。そして「自然や死者とともに『これから』をつくることへの確認」が必要なのであり、それこそが復興への道なのだ、と。
本書の中でもっとも重要な思想であるこの「死者とともに」作る未来という考え方は、決して著者の個人的な考えではなく、ついこのあいだまで日本人とその共同体が当たり前のようにもっていた考えであった。それは、本書のもうひとつのキーワードである「身体や生命のレベルの知」と深いかかわりがある、その事例として、著者は気仙沼のカキ養殖業者、畠山重篤氏を挙げる。
畠山さんは海の水質を守るために二〇年間に渡って、気仙沼湾にそそぐ大川上流の室根山に植樹をおこなってきた。それは「森は海の恋人」運動として知られている。被災した畠山さんは船も養殖場も失いながら、「それでも海を信じ、海とともに生きる」というメッセージを発信した。著者はその言葉に注目する。畠山さんのもっている「自然とともに生きてきた漁師の魂」、言葉を換えれば「生命そのもの」の知では、自然は恐怖であるとともに恵みでもある。その両方を身体が知っている。かつては当たり前にいた「自然のメカニズムを知性のレベルでも、身体や生命のレベルでも分っている人たち」にとって、自然はいかに脅威であっても、同時に恵みなのである。しかし、多くの人間が自然とともに仕事をしなくなってしまった戦後社会では、「恵み」と捉える感性が脱落した。あとは、恐怖しか残らない。自然をあくまでも屈服させ制御しようとする思想もまた、恵みの脱落なのであろう。
恵みは「身体や生命のレベル」で受け取るものであったが、それも脱落した。同時に、未来は死者の残したものの基盤の上で、死者とともに作るものだという考え方も、消えた。「生者」と「死者」の社会から、「死者」が脱落したのだ。「供養は共同体があってこそ真価を発揮する」と著者は書く。かつて葬儀は家族が出すものではなく共同体が出すものであった。そして皆が、死者とともに生きたのである。しかし死を受け止めるべき共同体が、この社会から脱落した。「共同体をとおして死を諒解(りょうかい)していった」人々は、もはやそれができなくなり、「不慮の死を不条理」としてしか考えられなくなったのである。
本書は極めて論理的に構成されている。生者と死者、自然の恐怖と自然の恵み、知と生命、個と共同体、情報と判断、崩壊と修復、それぞれの両方を私たちは持っているはずだった。しかしいずれもが、数十年の間にその片方を失(な)くした。死者、恵み、生命、共同体、自己判断能力、自己修復能力を失ったのだ。残ったのは、生の饗宴(きょうえん)、自然の恐怖、身体抜きの知、孤立する個、判断の役に立たないままふくれあがる情報、そして、個人の力では決して修復できないシステムの連鎖崩壊である。本書はその現実を「敗北」としてみつめる。そして「歴史が超えさせようとしているもの」に向かっている。
今私たちは新しい言葉が必要だ。本書にはその新たな言葉が随所にある。
http://mainichi.jp/enta/book/hondana/news/20111106ddm015070018000c.html