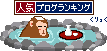遺体安置所で遺体と向き合う人々を追った壮絶ルポ『遺体 震災、津波の果てに』
http://image.news.livedoor.com/newsimage/a/f/af622_105_itai-m.jpg
2011年3月11日、日本列島に激震が走った。
東北地方の三陸沖を震源とするマグニチュード9.0もの巨大地震が起こり、宮城、福島、岩手県沿岸の町は、高さ10メートルを超える大津波に襲われた。もっとも被害の大きかった陸前高田などは、一瞬にしてひとつの町が丸ごと消えてしまった。
東日本大震災の死者・行方不明者は、およそ2万人。膨大な数の遺体が、津波で廃墟と化した町に散乱した。瓦礫の上に横たわる遺体、ちぎれてしまった腕や脚......。
本書『遺体 震災、津波の果てに』(新潮社)では、著者の石井光太氏が2カ月半という時間をかけ、被災地で200名以上に取材。その中から岩手県釜石市で遺体の収容や身元確認、葬送に当たった15人にフォーカスし、遺体とどう向き合い、どうやって立ち直って生きていこうとしているのかを追っている。
舞台となった釜石市では、旧二中(正式名称は釜石第二中学校)が遺体安置所となった。
釜石市は、釜石湾に面した人口4万人の小さな町で、海沿いの建物はことごとく流され、死者・行方不明者は1,000人を超えた。しかし、海沿いからたった1、2キロ先の国道1本を隔てた内陸側は津波の直接的な影響はなく、津波が発生した時どこにいたか、が生死の境となった。
それゆえ、生き残った人々は何十人もの顔見知りの死を受け止めながら、元・葬儀業者で遺体安置所の管理者を務めていた千葉淳氏を中心に、「自分たちにできることをしなければ」という思いで自発的に遺体安置所に集まった。市の職員は遺体を安置所へと運び、地元の医師や歯医者は身元確認を1日30体も40体も行い、必死に遺体と向き合っていた。
遺体安置所には行方不明者を捜す遺族が、次々にやってきた。市の職員や警察官にともなわれ、遺体を確認していく。
「これではありません」
「これも違います」
そして、突然の悲鳴が上がる。
「母です! 私の母です! ああ、やっぱりここにいた!」
娘は遺体に抱きつくようにしゃがみ込んで泣き始め、異常に静まった体育館内にその声が響いた。「もしも自分の家族だったら......」。その場に居合わせた人は、誰しもが自分自身と重ね合わせ、感情があふれそうになるのを必死でこらえていた。
そんな中、避難所に指定されている仙寿院の住職が訪れる。館内は歩く隙間もないほど遺体が並び、住職が故人の顔を見てみると、助けを求めるように口を開けていたり、逃れようと体をよじっていたり、水を飲んで苦しそうにしていたりし、どの顔にも浮かんでいるのは「苦痛」だった。
千葉氏が住職を案内する。
「彼女は臨月の妊婦なんです」
「この3人は家族なんです」
千葉氏は遺体の尊厳を守り、彼ら一人ひとりの名前や家族構成をしっかりと覚えていた。彼らのことを伝えることが使命とばかりに、涙を懸命にこらえ、丁寧に説明していく。そして、住職に提案する。
「ひとつ、お経を読んでくれませんか。そうしてくれると遺体も喜びます」
住職はうなずき、学習机でできた手作りの祭壇の前で、お経を読もうとする。
しかし、すぐ近くで幼い子どもの遺体にしがみついてしゃくり上げている女性の姿を目にし、涙腺がゆるんでいく。目をかたく閉じ、感情を押し殺してお経を続けようしても胸が苦しくなり、読経は途切れていった。
津波の恐ろしさがどんなものであったか。彼らが乗り越えようとしているものが何なのか。おそろしいまでの現実が、本書には詰まっている。
(文=上浦未来)
●いしい・こうた
1977年、東京生まれ。海外ルポをはじめとして貧困、医療、戦争、文化などをテーマに執筆。アジアの障害者や物乞いを追った『物乞う仏陀』(文藝春秋)、イスラームの性や売春を取材した『神の棄てた裸体』(新潮社)、世界最貧困層の生活を写真やイラストをつけて解説した『絶対貧困』(同)、インドで体を傷つけられて物乞いをさせられる子供を描いた『レンタルチャイルド』(同)、世界のスラムや路上生活者に関する写真エッセー集『地を這う祈り』(徳間書店)など多数。
http://news.livedoor.com/article/detail/6008508/